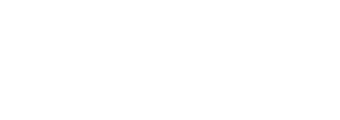緑内障
緑内障は、徐々に視野障害が進行する超慢性疾患で、我が国の中途失明原因の第1位です。今後さらなる高齢化が進むにつれて、緑内障患者は増加の一途をたどると予想されています。
日本医科大学緑内障外来では、緑内障診断・治療の向上に加えて、患者のQOLおよびアドヒアランスの維持・向上を目指し、主に臨床研究を中心に行なっています。以下、解説します。
緑内障の病態に関する臨床研究と知見
緑内障は、主に高眼圧による視神経乳頭の機械的障害により、網膜神経節細胞が徐々に変性・脱落していく疾患と考えられています。しかし、臨床的には循環障害、眼灌流圧(血圧―眼圧)、脳脊髄圧、眼圧変動など他の因子も複雑に影響しています。
- 私たちは、正常眼圧緑内障患者の左右眼の24時間眼圧と視野障害の程度から、症例を、眼圧依存性が高い可能性のある群と低い可能性のある群に分け、両者の眼灌流圧を比較して、後者の方が、有意に眼灌流圧が低いことを報告し、正常眼圧緑内障において眼血流障害が病態に関与する症例がある可能性を示しました。
- 脳脊髄圧の指標になる可能性を指摘されていたBody mass index (BMI)に関して、日本人の原発開放隅角緑内障と正常眼圧緑内障のBMIを比較して、欧米とは異なり、日本人においては両者の間に有意差がないことを報告しました。また、座位測定眼圧日内変動とBMIの関係を調べたところ、BMIが大きいほど、1日平均眼圧、1日最低眼圧が高く、眼圧変動幅が小さくなることを報告しました。
- 他に、視野検査後の眼圧変動と24時間眼圧日内変動の関係を調べ、視野検査前後の眼圧変動が大きいほど、夜間の眼圧が上昇している可能性も高いため、視野検査前後の眼圧変動が大きく、かつ、視野障害進行が認められる症例においては眼圧下降治療を強化する根拠となる可能性があることを報告しました(日眼会誌. 118 (10): 831-837, 2014)。
- その他、正常眼圧緑内障の腋窩温の検討、アンケート調査による緑内障患者の睡眠時間、睡眠パターン、既往歴について報告しました。
緑内障患者の無治療時眼圧変動
緑内障発症・進行の最大のリスクファクターは高眼圧ですが、外来眼圧のみならず、眼圧長期変動、眼圧日内変動、あるいは、体位変動(例えば、座位から仰臥位への体位変換に伴う眼圧上昇)などの眼圧変動も外来眼圧とは独立したリスクファクターの1つとされています。
- 私たちは、無治療時の広義原発開放隅角緑内障患者の24時間眼圧変動と眼圧体位変動に影響する因子を調べ、前者はBMIと午前10時眼圧、後者はBMIと年齢が有意に関係することを報告しました。
緑内障薬物治療の眼圧日内変動への効果
緑内障点眼薬の眼圧下降効果にも、薬剤の種類により特有の日内変動があります。
- 私たちは、各種プロスタノイド(FP) 受容体作動薬(ラタノプロスト、トラボプロスト、タフルプロスト、ビマトプロスト)、選択的EP2受容体作動薬(オミデネパグ)、β受容体遮断薬(チモロール、カルテオロール)、炭酸脱水酵素阻害薬(ラタノプロストとの併用におけるブリンゾラミド)、FP/β配合点眼薬(タフルプロスト/チモロール配合剤)、3剤併用点眼時(FP,β,CAI)の原発開放隅角緑内障における眼圧日内変動への影響について調べ、それぞれの薬剤の特徴について報告しました(Clin Ophthalmol 2021,Clin Ophthalmol 2018, J Ophthalmol 2017, Jpn J Ophthalmol, 2010, J Glaucoma 2007, あたらしい眼科 2012,日眼会誌 2004)。
- また、外来眼圧が低い進行性の緑内障患者の眼圧日内変動とCASIA2による隅角形状解析との相関関係を調べ、前房深度などいくつかのパラメーターが日内変動のパラメーターと有意に相関することを報告しました。
緑内障手術治療の眼圧変動への効果
緑内障手術治療というと、かなり病期が後期に至った時に行われるイメージがありますが、最近は、長寿高齢化や認知症を考慮して、また、点眼の副作用や複数の薬剤の併用によるQOL低下を改善させる目的で、比較的積極的に初期の段階から手術治療が行われつつあります。特に、選択的レーザー線維柱帯形成術(SLT)は、欧米では薬物治療に先行しておこなわれることが多くなっています。ただし、日本人でのSLTの効果におけるエビデンスが乏しいのが現状でした。そこで、我が国においても、現在、多施設共同でSLTの効果を評価する大規模な研究が行われています。
- 当科を含めた多施設研究で、正常眼圧緑内障におけるfirst-lineあるいはsecond-lineとしてのSLTの効果と安全性について報告しました(BMJ Open Ophthalmol. 2024)。また、当科では、SLTの眼圧測定時刻および施行季節による術後眼圧への影響を調べ、報告しました。
進行した緑内障あるいは多剤併用治療でも眼圧コントロールが不良の緑内障では、マイトマイシンC併用線維柱帯切除術が広く行われています。
- 私たちは、緑内障手術で広く行われているマイトマイシンC併用線維柱帯切除術後の広義の原発開放隅角緑内障における眼圧日内変動について調べ、1日平均眼圧が低いほど術後の眼圧変動が小さくなることを報告しました(臨眼 2006)。線維柱帯切除術で低く安定した眼圧を得るためにはできるだけ低い眼圧を目指す必要があることがわかりました。一方、線維柱帯切除術後、眼圧が日内変動を含めて低く安定していても、濾過機能が減弱し、薬物治療を再開すると、外来眼圧は下降しても眼圧日内変動が再び大きくなった症例についても報告しました(J Nippon Med Sch, 2021)
- その他、3剤併用薬物治療中の夜間眼圧上昇に選択的レーザー線維柱帯形成術が有効であった原発開放隅角緑内障の1例を報告しました。また、複数回の薬物治療時眼圧日内変動測定で夜間眼圧上昇を認めた原発開放隅角緑内障の1例に対してマイクロフックロトミーが眼圧変動抑制に有効であったことを報告しました(J Nippon Med Sch. 2024 )。
緑内障手術治療に関連するその他の臨床研究
マイトマイシンC併用線維柱帯切除術の効果が減弱した場合、通常、ニードリングによる濾過胞再建術を施行しますが、改善がない場合は観血的濾過胞再建術を施行します。
- 私たちは、マイトマイシンC併用線維柱帯切除術後の晩期合併症に対する有茎弁結膜被覆術の短期成績をまとめ、有効性を報告しました(日本医大雑誌,2014)。
緑内障進行を判定する際、視野検査のみならず、光干渉断層計(OCT)の網膜神経節細胞複合体厚(GCC)が有用ですが、眼圧変化によって測定値が変化するかについては不明でした。
- 私たちは、原発開放隅角緑内障において、GCCに対する眼圧の影響を調べるため、緑内障薬物治療およびマイトマイシンC併用線維柱帯切除術前後による眼圧変化とGCCの変化を調べたところ、臨床的にみられる眼圧変動ではGCCは統計学的有意な変化はないことがわかりました。
緑内障における角膜の臨床研究
原発閉塞隅角症の最初に行われるべき治療は、白内障手術あるいはレーザー虹彩切開術による手術治療です。しかし、レーザー虹彩切開術術は、角膜内皮細胞の障害による水疱性角膜症を数年後発症することがあることから、近年は白内障手術が第1選択とされています。
- 私たちは、原発閉塞隅角症に対するレーザー虹彩切開術(LPI)の角膜内皮細胞に及ぼす長期的影響について調べたところ、急性発作を起こしていない原発閉塞隅角症に対するLPIでは、角膜内皮細胞密度は、年間1.2%/年減少し、約40年間で半減する可能性があることを報告しました (あたらしい眼科, 2020)。
眼圧測定は、角膜を圧平して内圧を算出しています。角膜厚が厚いほど眼圧は高く測定されます。しかし、角膜厚も眼圧同様1日一定ではありません。
- 私たちは、原発開放隅角緑内障における中心角膜厚および角膜体積の日内変動を測定したところ、いずれも日中は減少し夜間は増加する日内変動を示したことを報告しました。
また、緑内障治療薬によっても、角膜厚は変化します。
- 私たちは、原発開放隅角緑内障におけるラタノプロストと塩化ベンザルコニウム非含有トラボプロスト点眼前後の角膜厚および眼圧変化を調べて、 両者ともに角膜厚が有意に減少し、中心角膜厚の減少率が大きいほど、眼圧下降率が大きくなることを報告しました(あたらしい眼科, 2010)。
緑内障手術後の乱視変化に関する研究
緑内障手術で広く行われているマイトマイシンC併用線維柱帯切除術は、眼圧下降効果が優れている一方で、他の緑内障手術と比較しても、手術後の乱視変化(惹起乱視)が大きいことが知られています。緑内障手術後の惹起乱視は視機能に影響する大きな問題ですが、乱視変化の要因やその対処法については、まだあまり多くの研究は行われていません。
- 私たちは、マイトマイシンC併用線維柱帯切除術後の惹起乱視は、手術時の強膜弁の作成方向に角膜カーブが急峻化する傾向があること、また、惹起乱視の大きさは、強膜弁縫合糸数、レーザー切糸後の強膜弁縫合糸残数が大きいほど大きくなる関係があり、強膜弁縫合糸が惹起乱視の主要な原因であることを報告しました。(Clin Ophthalmol, 2022)
- 私たちは、マイトマイシンC併用線維柱帯切除術後の惹起乱視は、術後3年間の長期経過でもその大きさの平均はほとんど変化しないこと、ベクトル平均は徐々にシフトし、術後1年目以降にほぼ安定化することを報告しました。
- 私たちは、マイトマイシンC併用線維柱帯切除術後の惹起乱視が大きい症例の白内障手術において、トーリック眼内レンズ(乱視矯正用眼内レンズ)の使用が有用であることを報告しました。
おわりに
私たちは、現在行われている治療の質を評価する研究を主に行なってきましたが、今後はQuality of Vision(QOV)の維持のみならず、QOLの向上を目指した治療の研究・開発をしていきます。